最近さまざまなメディアで、声優が朗読をするオーディオブックなるものが流行っているようです。
朗読の歴史は古く、絵本の読み聞かせなども朗読の部類に入ります。
声優の仕事の一つとして朗読というジャンルもあります。
今回は、朗読がどんなものなのか、朗読が上手くなる6つのコツをご紹介します。
朗読ってどんなもの?
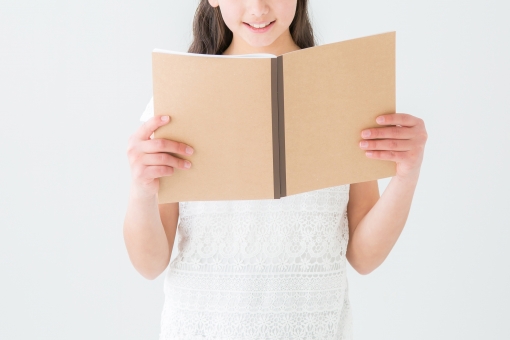


朗読と聞いてパッと答えられる人は、朗読の好きな人だと思います。
アニメのセリフや吹き替えのセリフ、ナレーションとも全く違うジャンルのものです。
まずは朗読がどんなものなのかご紹介していきます。
【1】朗読とは?
朗読とは「声をあげて文章や詩歌を読むこと」と定義づけられています。
しかもただ読むだけではなく「朗々と」と言う意味も含まれています。
ちょっと意味が分かりづらいですね。
簡単に言うと「感情を込めて文章や詩歌を読むこと」が朗読です。
【2】音読・読み聞かせとの違いは?
昔小学校の国語の授業で教科書を読み上げる「音読」をやったことがある人は多いでしょう。
音読についても朗読の一部だと言う定義付けをしているものもあります。
しかし音読と朗読は「気持ち」があるかないかで、意味合いが若干変わります。
ココがポイント
音読は文章を声に出して読むこと。
朗読は「気持ちを込めて」文章を声に出して読むことです。
他にも「読み聞かせ」という似たような言葉を聞いたことがある人もいると思います。
読み聞かせは比較的低めの年齢層に向けて、絵本などを音読することを言います。
また朗読のように「気持ちを込めて」読み上げることも読み聞かせの一部です。
読み聞かせと朗読は、対象となる年齢層も違います。
また読み聞かせの場合、絵本などを題材にするため、「絵を見ながら」朗読をするという違いもあります。
【3】朗読は別名「表現読み」
音読とは違い朗読は「気持ちを込めて」文章を読むため、読み手によって表現の仕方が変わってきます。
朗読のことを別名「表現読み」というのはこのためです。
しかし細かく分析していくと朗読と表現読みは異なるという人もいるので、境目があいまいです。
最近では音読と朗読の違いもあいまいになってきています。
さらに他にも「語り」などという言葉もあり、定義をする人によっても解釈が異なっているため明確な境目はあまりないと思われます。
今回ご紹介する朗読のコツは、表現読みに近い朗読ということで話を進めていきます。
声優の仕事の1つ「朗読」

声優養成所や声優専門学校でのレッスンで、朗読のジャンルに触れることがあります。
セリフやナレーションと明確に違うポイントもあります。
しかし、「気持ちを込めて」文章を読み上げること=朗読なのであれば声優の仕事の一つということになります。
【1】声優の仕事は文字を音声で表現すること
セリフ、ナレーション、朗読。この三つに共通することは文字を音声で表現することです。
声優の仕事は、台本に書かれた文字を音声として「再生」することとよく言われます。
この「再生」 されたものを人が聞いて、心を動かすまでが声優の仕事です。
【2】声優によるオーディオブックってなあに?
声優による「オーディオブック」というのが、色々なメディアで話題になっているのはご存知でしょうか。
これは本の内容を朗読やナレーションで聞かせるものです。
ラジオドラマも近いジャンルではありますが、 ラジオドラマでは何名かの声優が台詞やナレーションを吹き込んでいるのに比べ、オーディオブックでは一人の声優が、主に書籍を朗読して物語を伝えるという意味合いが主流です。
実はオーディオブックは、日本では1980年代からすでにあったものです。
その頃はオーディオブックという名称ではなく「カセットブック」 でした。
その後 CDブックという名称でも呼ばれ、カセットやCDという媒体だけでなく、IPodやウォークマンなどさまざまな媒体を通して朗読を聴けるようになりました。
それを総称してオーディオブックと呼ばれています。
朗読が上手くなるコツ ~基礎編~



「セリフは得意だけど、朗読は苦手・・・」「ナレーションなら好きだけど、朗読のコツがわからない」という人は結構います。
でも基本はセリフもナレーションも朗読も同じなので、まずは台本をよく読むことから始めましょう。
例題を見ながら、解説していきますね。
【例題】
気が付いた時には日は周って清々しい日差しが木陰まで入ってきていた。
木こりは目を細めて眩しげに紺青の空を見上げていたがのっそりと立ち上がると大きなあくびをした。
「いいあんばいだ、このぶんだと当分日和続きだな」
和やかな顔をしてきこりは斧を肩に急勾配を降り始めた。ゆっくりゆっくり木こりは下ってゆく。
すると雑木林の木の間隠れにないだ海が見え始めた。
いきなり声に出して読むのはおすすめしません。
まずは黙読でこの文章が何を言いたいのかどんな状況を伝えたいのかを考えます。
【コツ1】間のとり方を工夫する
日本語の文章は「。」「、」で区切られています。
これはただの記号ではありません。
意味としては、文章と文章の、または文節と文節の切れ目を表しています。
これを朗読しようとした時には、「間をとる」という意味になります。
かなり基本的なところにはなりますが「。」は句点、「、」は読点と呼ばれます。
句点は少し長め、読点は短い間をとることが共通認識です。
今度は、句点と読点に気を付けて、例題を「音読」してみましょう。
ココがポイント
細かく解説すると、句点や読点以外にも間をとることで、文章の意味や伝えたいことが聴いている人に伝わりやすくなります。
間のとり方はさまざまなので、相手にどう伝わってほしいかを考えて工夫することがポイントです。
【コツ2】抑揚をつける
ただ読むだけの音読だと、聞いている人はいわゆる棒読みに近いものになります。
日本語の文章の中で基本的な抑揚の付け方は、文章の最初を高く、文章の最後を低くすることです。
この抑揚の付け方でもう一度例題を読んでみましょう。
【コツ3】接続詞に変化をつける
先ほどご説明した抑揚のうち、接続詞に変化をつけることで表現が変わってきます。
この例題の場合一番最後の文章。
「すると雑木林の~」ですね。
「すると」という接続詞が、それまでの風景から一転していることを示します。
その後の風景が全く違ってしまうとか、とてもドラマチックなことが起こるなどを予感させます。
接続詞は、接続詞によって色々な意味合いがあるので、その意味によって変化をつけると、聞き手の興味を引くことができるのです。
この例題の場合、「すると」という接続詞で、シーンが変わる可能性が高くなったことを示しています。
少し間をとって、声も高めに発することで、変化をつけることができます。
朗読が上手くなるコツ ~応用編~



朗読が上手くなるコツとして、基本的な日本語の読み方をお伝えしました。
でもまだまだ朗読までには至っていません。
もう少し掘り下げて説明していきます。
【コツ4】立てる
例題の文章をひとまとまりで考えるのではなく、文章ごと、文節ごとに分解します。
全体の文章の中でも「この文章が何を伝えたいのか」、一つの文章の中でも「何が重要なのか」を意識します。
細かく分けていくことで、どの文節が重要なのか理解することが大切です。
基礎編でご紹介した接続詞が、「立てる」というテクニックの一部です。
他には、「のっそり」とか 「ゆっくりゆっくり」とか、この文章全体の雰囲気を伝えるキーワードがたくさんありますね。
イメージとしては「のんびりした」というものになるかと思います。
言葉の立て方は本当に様々で、次にご紹介する視点の変化やスピードなどでも変わってきます。
【コツ5】視点の変化
例題では大きく分けると地の文とセリフに分かれています。
「地の文」とは、セリフではない部分を指します。
ココがポイント
地の文の読み方も色々あるのですが、オーソドックスなやり方としては第三者の視点で読むのが基本です。
カメラワークに例えると、主人公を「聴き手」が見ているような視点です。
そしてセリフの視点は、木こりの視点ですね。
セリフの部分では木こりが見ている風景が見えている状態です。
視点の変化を意識することで、さらに抑揚がつけやすくなります。
さあもう一度例題を読んでみましょう。
【コツ6】スピードを考える
一定のスピードで読んでしまうと、抑揚があったとしても、平坦に聞こえてしまいます。
そこでスピードを考えてみます。
例題では、この木こりは仕事で取りに来ているわけですが、文章全体で考えるとゆったりとしたイメージが湧いてくると思います。
そのため、スピードとしては全体的にゆっくりになるわけです。
さらに細かく考えてみます。 先ほど説明した視点の変化でセリフのところは特に木こりの気持ちが表れています。
晴れて嬉しい、リラックスしているという気持ちであることは分かりますね。
全体的な文章の読み方はゆっくりです。
さらにセリフのところでは、木こりの気持ちになると、「いいあんばいだあ」「当分日和続きだなあ」というように最後に「あ」をつけたような表現をすると、伝わりやすくなります。
もちろん、スピードはゆーーっくりにしてもいいでしょう。
まとめ


今回ご紹介した例題の文章だけでも、細かく分析していくと表現方法は無限大にあることがわかります。
人によって口調やテンポ、スピード、抑揚の付け方もさまざまです。
まずは短い文章から朗読を練習してみましょう。
練習する時は、必ず録音するようにしてください。
文章を細かく分析しどう表現していくかを考えていく作業を繰り返し行うことで、表現の幅も広がります。
一流の声優は朗読も上手いことは間違いありません。朗読が上手くなれば声優になることにも近づくということです。


